頭痛鎮痛薬を頻回に使用することで悪化するケースもあります

今、あなたが感じている頭痛。その痛みに対して鎮痛薬を服用し、症状をやわらげる、これは一つの対処法です。間違いとは言えませんし、必要な対応である場面もあります。
そのような薬による対処を続けてしまうと、むしろ事態は悪化してしまいます。本来は「片頭痛」や「緊張型頭痛」など、原因がある頭痛だったはずが、そこにもう一つ、厄介な病名が加わることになるのです。
それが、「薬物乱用頭痛」です。
この薬物乱用頭痛は非常に厄介で、頭痛を抱えている方の中でも、特に重篤な状態と考えなければなりません。ただ単に頭痛が良くならないというだけでなく、鎮痛薬を手放せなくなり、いわゆる「薬物依存」の状態にまで進行してしまっていることが多いからです。
こうした状態にある、あるいはその可能性があると診断された場合には、できるだけ早く頭痛の専門外来を受診し、適切な治療を受ける必要があります。放置すればするほど、薬を減らすことも困難になり、日常生活にも大きな支障をきたすようになります。
「薬でなんとかする」という発想から、「根本的に治していく」方向へと、一歩踏み出すことが大切です。
薬剤乱用頭痛について
薬剤乱用頭痛は、頭痛を抑えるために使っていた鎮痛薬や片頭痛治療薬を、長期間かつ頻繁に使用し続けた結果、かえって頭痛が慢性化・悪化してしまう病気です。特に片頭痛や緊張型頭痛を持つ人が、薬を月10〜15日以上使用し続けることで発症しやすくなります。
症状としては、ほぼ毎日頭痛が起こり、薬の効果も次第に薄れていきます。また、薬をやめると一時的に頭痛が強まる「離脱症状」が現れることもあります。
治療には原因となっている薬の中止や減量、予防薬の導入、生活習慣の見直しなどが必要です。自己判断での対処は危険なため、専門医の診察を受けることが重要です。
早期の対応により改善が見込めるため、「薬を飲みすぎているかもしれない」と感じたら、早めの相談をおすすめします。
薬剤乱用頭痛の診断方法
詳細な問診
- 頭痛の頻度(月に何日程度起こるか)
- 使用している薬の種類と服用回数(月に何回使用しているか)
- 薬の効果や効き方の変化
- 頭痛の性質の変化(痛みの強さ・場所・時間帯など)
頭痛日記の活用
- ご自身の頭痛のパターンや薬の使用状況を把握するために、頭痛日記の記録をお願いすることがあります。頭痛が起きた日時、痛みの程度、薬の服用タイミングとその効果などを記録していただくことで、より正確な診断につながります。
以下のような国際頭痛分類第3版(ICHD-3)に準拠し診断します
- 頭痛が月15日以上ある状態が3か月以上続いている
- 鎮痛薬や頭痛治療薬を、月に10日以上(薬の種類によっては15日以上)使用している
- 薬の過剰使用を減らすことで頭痛が改善する傾向がみられる
必要に応じた画像検査
- 頭痛の原因が薬の使用によるものか、それ以外の病気(脳腫瘍や脳出血など)によるものかを区別するために、必要に応じてMRI検査を行う場合があります。
薬剤乱用頭痛の治療
原因となっている鎮痛薬の乱用をまず早期に中止する必要があります。しかし、頭痛があるのに鎮痛薬を使用することができなくなるわけですから、当然その部分に対するケアが必要となってきます。そこで重要となるのが、適切な予防療法というわけです。
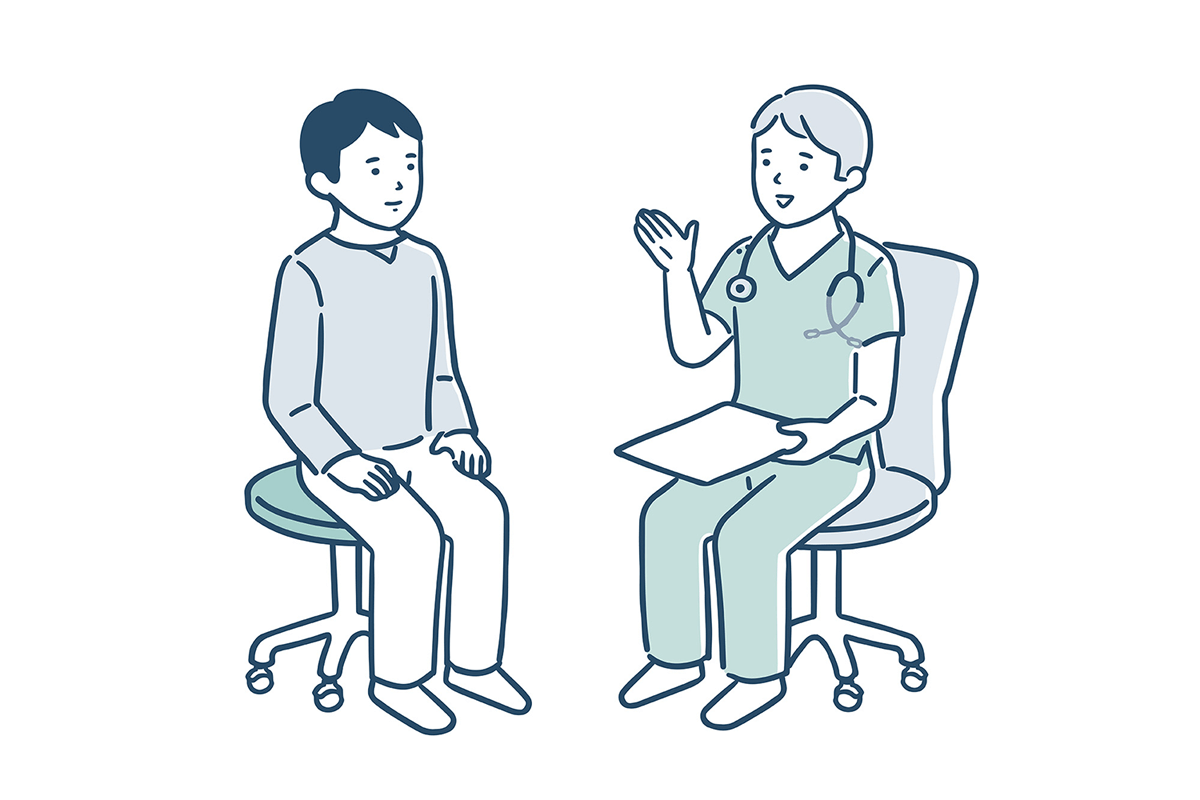
原因薬の中止または漸減(ぜんげん)
最も重要なのは、原因となっている薬剤の使用を中止するか、少しずつ減らしていくことです。ただし、急にやめると頭痛が強くなったり、不安感や不眠といった「離脱症状」が出ることもあるため、医師の指導のもとで慎重に進める必要があります。
頭痛の予防治療の導入
薬を減らすと同時に、もともとの頭痛(片頭痛や緊張型頭痛など)に対する予防薬を導入します。予防薬により頭痛の頻度や強さを減らし、鎮痛薬に頼らない状態を目指します。患者さまの症状に合わせて、最適な薬を選択していきます。
生活習慣の見直し
頭痛は生活習慣とも深く関係しています。以下のような点を一緒に見直していきます
- 睡眠の質とリズム
- 食生活(特定の食品や空腹が引き金になることも)
- ストレス管理
- 適度な運動やリラックスの習慣
継続的なフォローアップ
薬剤乱用頭痛の治療は一度で完了するものではありません。定期的に状態を確認し、治療効果を見ながら方針を調整していきます。当院では、頭痛に詳しい医師が丁寧に経過を見守りながらサポートいたします。
頭痛ダイアリーをご活用ください
頭痛ダイアリーとは、日々の頭痛に関するさまざまな情報を記録していく、いわば“頭痛の記録帳”です。
このダイアリーを活用することで、「いつ頭痛が起こったのか(頭痛の日数)」、「どのような種類の痛みだったか(頭痛の性状)」、「痛みの強さ」「どれくらいの時間続いたか(持続時間)」、「頭痛に伴って現れたその他の症状(随伴症状)」、「どのようなことが引き金となったか(誘発因子)」、「頭痛薬をいつ、どのくらい使用したか(薬剤使用状況)」、「日常生活にどの程度の支障が出たか(生活支障度)」といった詳細な情報を記録・把握することができます。
このような記録は、医師が診察を行う際、通常の問診だけでは得られにくい情報を補い、頭痛の種類や原因をより正確に判断するための手がかりとなります。その結果、個々の患者さんに合った適切な診断や治療方針の決定に大きく寄与します。
また、患者さんご自身にとっても、どのような状況やタイミングで頭痛が起きやすいのか、自分の頭痛の傾向を客観的に見つめ直すことができ、予防やセルフケアにも役立ちます。
特に、慢性的な頭痛や重度の頭痛に悩まされている方にとっては、頭痛ダイアリーは診療における“必須のツール”と言っても過言ではありません。症状の改善や生活の質の向上を目指すためにも、ぜひ積極的にご活用いただくことをおすすめします。



